スポーツビジネス入門(1/3)〜スポーツビジネスの全体像を知る〜
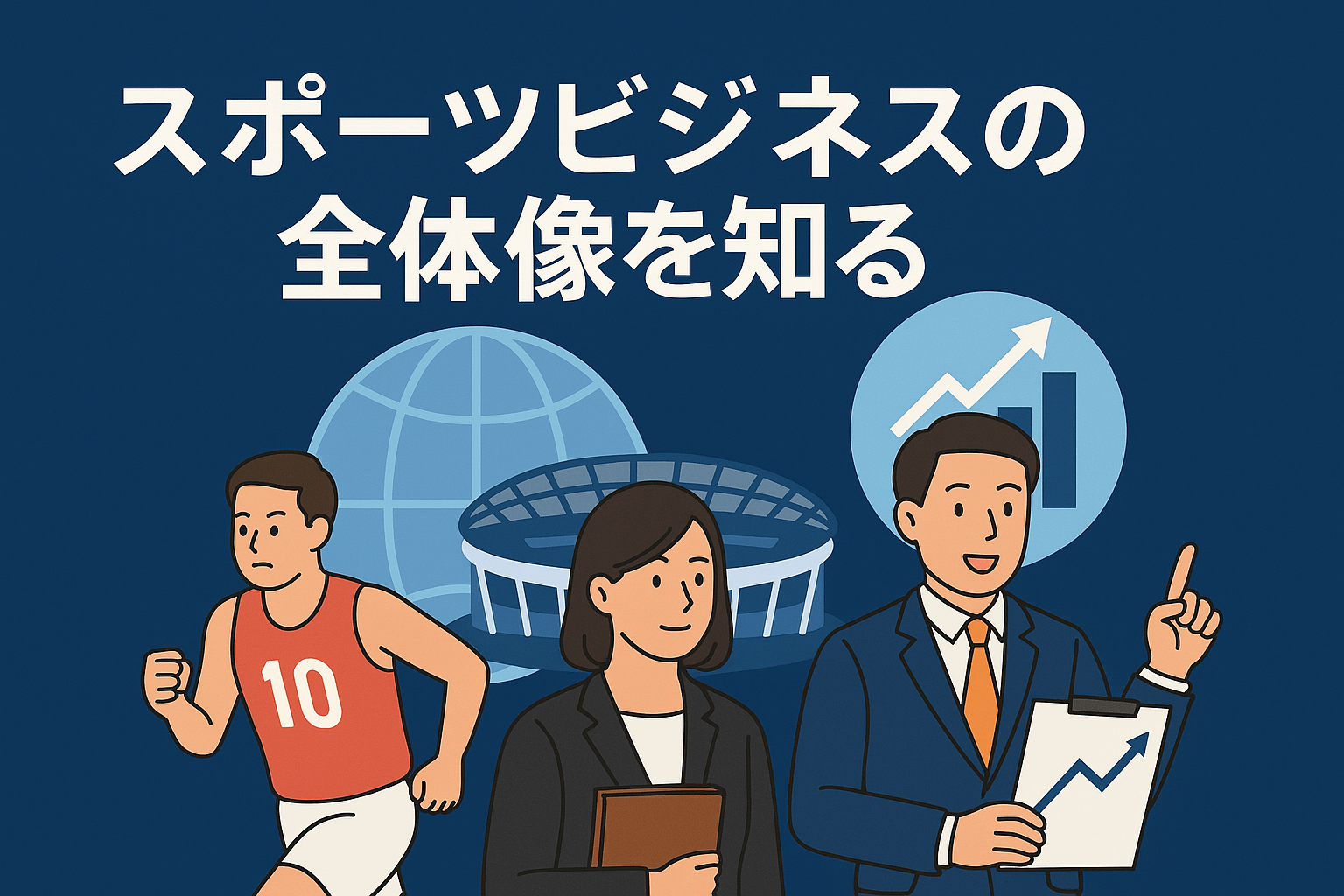
本コラムでは全3回に分けて「これからスポーツビジネスを学びたい」「体系的にスポーツビジネスを学びたい」という方向けに、スポーツビジネスの基礎知識をお伝えしていきます。 第1回のコラムは、「スポーツビジネスとは何か?業界の全体像を理解する」を目的に、以下について学びます。 ・スポーツビジネスの定義と歴史 ・スポーツ業界の構造(プロ・アマ、団体・企業) ・スポーツビジネスの種類(チーム運営、イベント、スポンサーシップ、メディア、グッズ販売など) ・市場規模とトレンド
スポーツビジネスとは?
スポーツビジネスの定義
スポーツビジネスとは、スポーツを軸として「商品」「サービス」「体験」を提供し、経済的価値を生み出す産業全体を指します。
競技や選手の活躍そのものにとどまらず、以下のような幅広い活動が含まれます。
- イベント
- メディア
- スポンサーシップ
- 施設運営
- ファングッズ
- スクール事業
など、幅広い活動が含まれます。
つまり、スポーツを「楽しむ」「支える」「広める」あらゆる活動がビジネスに結びついています。
歴史的背景
スポーツが経済活動と結びつくようになったのは20世紀後半からとされます。
テレビ放映の普及によって、スタジアムに行けない人々にもスポーツを届ける手段が生まれ、スポンサー企業が注目するようになりました。
例えば、オリンピックやワールドカップなど国際大会のスポンサー料や放映権収入は、数千億円規模にまで成長しています。
スポーツビジネスの特徴
スポーツビジネスには以下のような特徴があります。- 高い感情価値:スポーツには人々の心を動かす力があります。ファンの熱狂や応援は、他の商品・サービスとは異なる強いつながりを生み出します。
- 多様なステークホルダー:選手、チーム、ファン、スポンサー、メディア、行政など、多くのステークホルダーが関与します。
- 社会的意義:地域活性化や教育、健康促進など、社会課題の解決にも貢献する側面があります。
現代のスポーツビジネスの例
常に時代に合わせてスポーツビジネスの形は変化しています。そのような中、現代のスポーツビジネスは以下のような形がメインです。
- プロチーム運営:チケット収入、放映権、スポンサー、グッズ販売など多様な収益源を持つビジネスモデル。
- スポーツイベント企画:マラソン大会、フェスティバルなどを通じて地域との関係性や観光需要を創出。
- デジタルコンテンツ:YouTubeやSNSでのライブ配信、ファンエンゲージメント施策など、新しい形の収益モデルも登場しています。
スポーツ業界の構造
スポーツ業界のプレイヤー
スポーツ業界には、以下のように多様な関係者(ステークホルダー)が関わっています。
※カテゴリごとに主なプレイヤーを紹介します。
- 団体:国際スポーツ連盟、国内競技連盟、JOC、Jリーグなど
- チーム・クラブ:プロチーム、アマチュアクラブ、大学・高校の部活動
- メディア:テレビ局、YouTubeチャンネル、配信プラットフォーム
- スポンサー:ナイキ、アディダス、飲料メーカー、通信会社など
- サービス業者:イベント会社、警備、交通、宿泊、飲食業者など
- ファン・観客:一般消費者、ファンクラブ、地元住民など
それぞれの役割と関係性
上記で紹介した各カテゴリには、以下のような役割と関係性があります。
- 団体:ルールの整備、競技大会の運営、国際組織との連携などを行います。
- チーム・クラブ:選手の育成、地域との関係構築、試合の興行収入などに携わります。
- メディア:試合の放送や情報発信により、視聴者・ファンの獲得とスポンサー価値の向上を担います。
- スポンサー:金銭的・物品的支援を通じて、ブランド価値の向上や社会貢献を図ります。
- ファン・観客:チケットやグッズ購入、SNSでの応援などでビジネスを支える主役です。
なぜ業界の構造を理解するのが必要なのか?
スポーツビジネスに関わるには、業界の構造や役割分担を理解しておくことが大切です。
それぞれの立場や目的が異なるため、利害調整や連携がスムーズに進む基盤となります。
スポーツビジネスの主なジャンル
スポーツビジネスは様々な形で展開されています。
ここでは、主要なジャンルとその特徴、具体的な事例について解説します。
主なジャンルと特徴
1.プロチーム運営
選手契約、チケット販売、グッズ販売、スポンサー契約、ファンイベントの開催など。
例:Jリーグクラブやプロ野球チームのビジネスモデル。
2.スポーツイベントの企画・開催
市民マラソン、スポーツフェスティバル、国際大会など。
収益源:参加費、協賛金、物販、飲食、観光連携など。
3.スポンサーシップビジネス
企業がチーム・大会・選手に協賛することで、広告・販促・CSR効果を得る。
提供されるもの:看板表示、ユニフォームロゴ、CM連動、SNS投稿など。
4.メディア・放映権
試合の中継、ハイライト映像、バックステージの配信。
DAZN、YouTube、TVerなどが市場を変化させている。
5.ライセンス・グッズ販売
チームグッズやキャラクター商品などを通じたブランド強化と収益化。
オンラインショップやポップアップストア展開も一般的。
6.スポーツ教育・指導ビジネス
スクール運営、アスリート育成、セミナー開催。
例:キッズサッカースクール、トップ選手のクリニック。
スポーツビジネスの市場規模とトレンド
日本国内の市場規模
経済産業省や民間調査によると、国内スポーツの市場規模は約13.7兆円(2021年推計)で、以下の要素が主要な構成要素です。
- プロスポーツ興行
- スポーツ用品・アパレル
- フィットネス・ジム
- スポーツイベントや観光
- 教育・育成事業
政府は「スポーツの市場規模を2025年に15兆円規模に拡大する」というビジョンを掲げています。
世界市場の動向
世界のスポーツ市場は6000億ドル以上の規模で増加の一途を辿っています。
ここ数年の主なトピックは以下の通りです。
- 成長の著しい領域:eスポーツ、女性スポーツ、アジア市場、スポーツテック
- アメリカ:NFL、NBAなどメジャーリーグが高収益体質。
- 欧州:サッカーリーグを中心にグローバル市場で拡大。
注目のトレンドキーワード
スポーツビジネスを学ぶ上で、ここ最近の注目として以下については把握しておくのが重要です。
- デジタル化・配信革命:DAZNやスポーツ専用アプリの登場で、視聴者の獲得方法が多様化。
- ファンエンゲージメント:SNSやアプリを通じた参加型施策が主流に。
- スポーツ×地域創生:クラブと地域の連携で観光・教育・健康づくりと連動。
- サステナビリティの重視:大会運営の脱炭素化、リサイクルユニフォームなどの取り組み。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、スポーツビジネスを学ぶ上での全体像を簡単に把握してもらう回となりました。
全体像を理解することで、業界全体の構造が簡単に把握でき、実際のスポーツの現場でも理解が進みやすくなります。
次回以降は、本コラムで紹介した内容を少し深掘りしながらご紹介していきます。


