スポーツ業界を目指す就活生の「勘違い」5選 ――「スポーツが好き」だけでは通用しない!本当に求められる視点とは
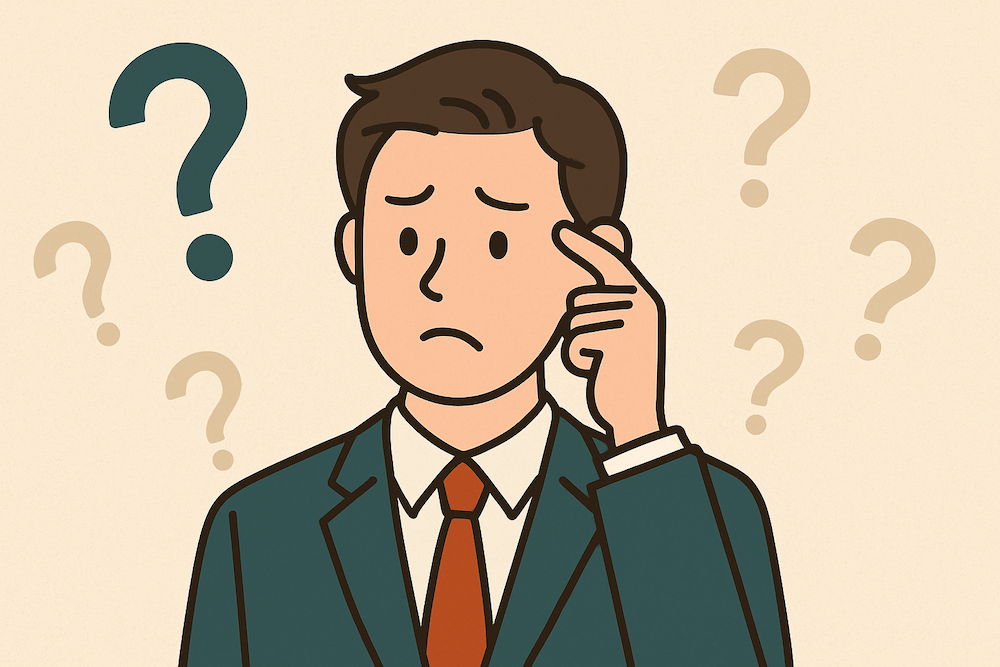
スポーツ業界を志望する学生は年々増えています。 プロチーム、スポーツメーカー、スポーツメディア、地域スポーツ団体、スタートアップなど、活躍の場も多様化しています。 しかし、いざ就職活動を始めてみると「こんなはずじゃなかった」「思っていた業界と違った」と壁にぶつかる学生も少なくありません。 その背景には、「スポーツ業界=〇〇」といったイメージ先行の「勘違い」があることが多いです。 今回は、スポーツ業界を目指す就活生がよく陥りがちな5つの「勘違い」とその「対処法」についてご紹介いたします。
【勘違い①】「スポーツ好き」だけで内定が取れる
「スポーツ業界で働きたい理由は?」という問いに対して、「スポーツが好きだから」と答える学生は非常に多いです。しかし、これはあくまで「入口の動機」であり、それだけでは説得力がありません。
企業側が求めているのは、「好き」から一歩踏み込んだ「貢献意欲」や「課題意識」です。
例えば、「スポーツ観戦が趣味だからJリーグで働きたい」という学生には、「Jリーグの何に課題を感じ、どう改善したいか」という視点が求められます。
また、採用担当者からは「好きなことを仕事にすると、現実とのギャップに失望しやすい」との声もあります。
スポーツビジネスの現場は、泥臭い営業、地道な広報活動、緻密なスケジュール調整など、「非華やか」な仕事が多いのです。
もちろん「好き」から始めてOKですが、必ず「どう貢献したいか」「どんな課題を感じているか」という視点を加えることが大事です。
OB・OG訪問やインターンを通じて現場のリアルに触れ、自分なりの仮説を持つようにしてみましょう。
【勘違い②】「アスリート経験」があれば評価される
例えば、「部活で全国大会に出場した」「大学で主将を務めた」というような経歴はもちろん素晴らしいものですが、それだけで内定につながるわけではありません。実際には、企業が見ているのは「その経験から何を学び、どう行動したか」です。
「主将としてどのようにチームをまとめたか」「スランプをどう乗り越えたか」といったエピソードが評価対象になります。
また、アスリート経験があるがゆえに、「結果を出せば評価される」「上下関係に従えばOK」という「スポーツの文脈」をビジネスにそのまま持ち込んでしまう人もいます。
また、アスリート経験があるがゆえに、「結果を出せば評価される」「上下関係に従えばOK」という「スポーツの文脈」をビジネスにそのまま持ち込んでしまう人もいます。
これでは、チームプレーも自律性も求められるビジネス現場には対応できない可能性があると判断させてしまうこともあります。
そのため、経験そのものよりも、「思考」と「行動」にフォーカスして自己分析を行いましょう。
そのため、経験そのものよりも、「思考」と「行動」にフォーカスして自己分析を行いましょう。
具体的なエピソードを言語化し、「どんな力が身についたか」を示すことが大切です。
【勘違い③】「プロチーム=花形部署」で働ける
プロ野球やJリーグ、Bリーグなどのチームに憧れて就活を始める学生も多くいます。「試合の演出を考えたい」「SNS運用をしたい」「選手のそばで働きたい」など、そういった夢は大切ですが、現実には新卒でいきなり花形部署に配属されることはほぼありません。
多くのクラブチームでは営業(チケット販売やスポンサー営業)、総務(地域連携や行政対応)といった「縁の下の力持ち」的な業務が中心です。
多くのクラブチームでは営業(チケット販売やスポンサー営業)、総務(地域連携や行政対応)といった「縁の下の力持ち」的な業務が中心です。
イベント現場やグッズ売り場などに立つことも多く、「体力勝負」な日々が続くケースもあります。
そのため、「クラブを支える仕事とは何か」を事前に調べましょう。
そのため、「クラブを支える仕事とは何か」を事前に調べましょう。
クラブの採用ページやインターン体験談、現場で働く社員のSNSなどから実務の実態を把握することが重要です。
【勘違い④】「有名企業」ならやりたい仕事ができる
ナショナルスポンサーやメディア露出の多い企業に憧れる気持ちは自然です。しかし、「有名な会社に入ればスポーツに関われる」と考えるのはやや危険です。
例えば、大手スポーツメーカーに入社しても、最初は営業職で量販店を回ることが多く、商品企画やマーケティングにはすぐに関われません。
例えば、大手スポーツメーカーに入社しても、最初は営業職で量販店を回ることが多く、商品企画やマーケティングにはすぐに関われません。
また、大手広告代理店でもスポーツ案件に携われるのは一部の人材に限られ、配属は運次第ということもあります。
そのため、「企業名」よりも「業務内容」に注目してみましょう。
そのため、「企業名」よりも「業務内容」に注目してみましょう。
募集要項に書かれている仕事内容や、若手社員のキャリア事例をよく確認し、自分の希望とマッチしているかを見極めることが重要です。
【勘違い⑤】「スポーツ業界」は狭き門
「スポーツ業界は人気だから内定が取れない」と思い込んで、最初から諦めてしまう学生もいます。しかし、実際には中小のスポーツ企業や地域密着クラブ、スポーツ系スタートアップなど、チャレンジの余地は十分にあります。
また、いわゆる「スポーツ業界」ではなくても、スポーツに関わる仕事は無数にあります。
IT企業がスポーツ観戦アプリを開発したり、物流企業がスタジアム納品を担っていたりと、「間接的にスポーツを支える」選択肢も広がっています。
選択肢を増やすには「スポーツに関わるキャリアの多様性」を知ることが重要です。
選択肢を増やすには「スポーツに関わるキャリアの多様性」を知ることが重要です。
業界地図や関連書籍、業界別インターン募集サイトなどを活用し、視野を広げましょう。
「直接関わる/間接的に支える」の両方を視野に入れると、選択肢は格段に増えます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
スポーツを「好き」で終わらせず、「自分はどんな立場で貢献できるか」「業界のどんな課題を解決したいか」といった視点を持つことで、志望動機は深みを増します。
就活はゴールではなく、キャリアのスタートラインです。
就活はゴールではなく、キャリアのスタートラインです。
現実と向き合いながらも、自分らしいキャリアを切り拓く第一歩として、この記事がヒントになれば幸いです。
無料会員登録していただいた学生の皆さまへは会員限定のお得な情報を配信いたします。


