スポーツビジネス入門(2/3)〜ビジネスの基本を押さえる〜
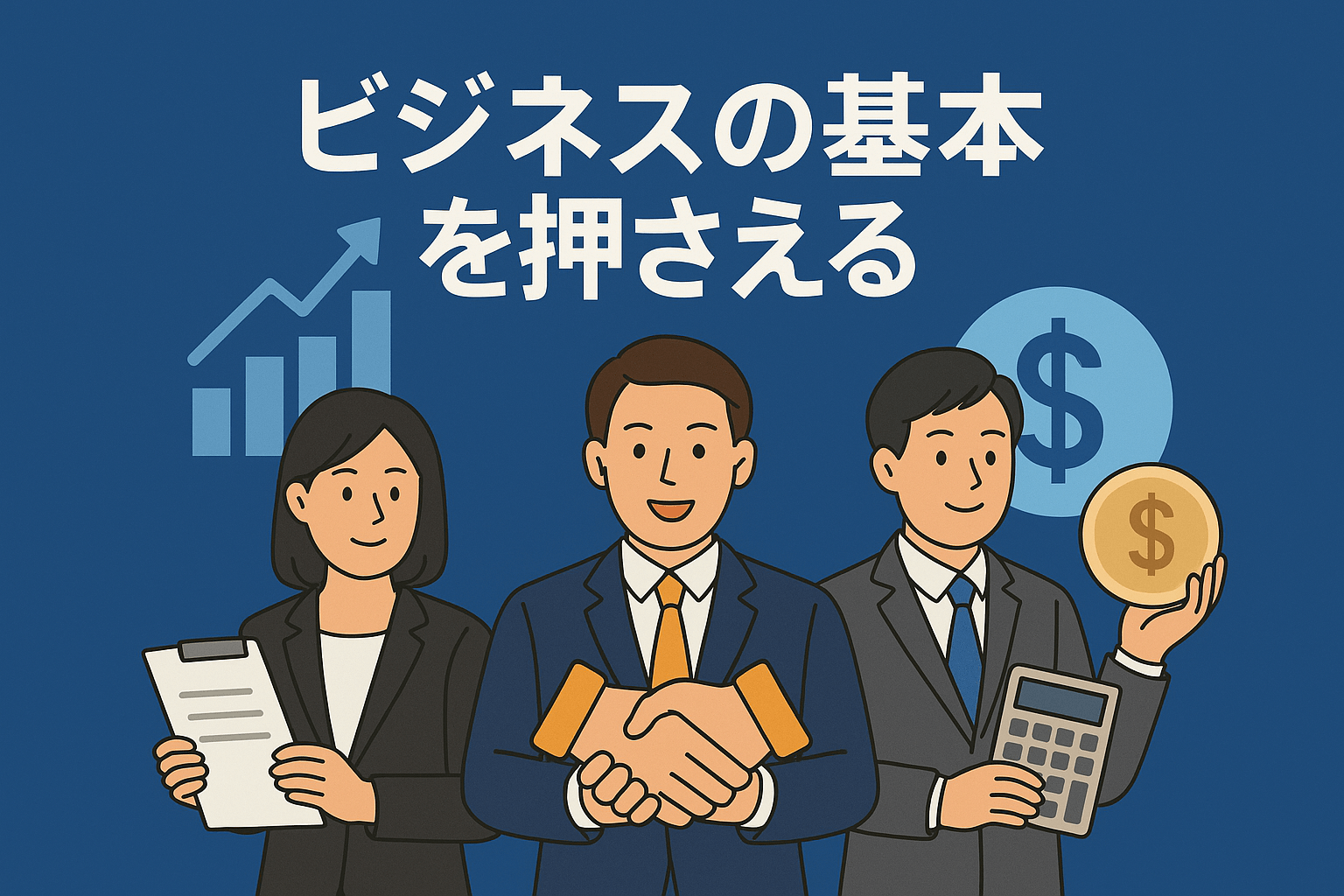
スポーツビジネスに関わる上で、どれだけスポーツに対する情熱や興味があっても、「ビジネスとして成り立つ」というものがなければ、継続も拡大も難しいのが現実です。 そこで重要になるのが「ビジネスの基本構造」を理解すること。 つまり、どんなビジネスでも共通して求められる【価値の創出→提供→対価の回収】の流れを体系的に捉える力です。 本コラムでは、どのようにビジネスは仕組みとして回っているのかを、スポーツの現場に即して解説します。 (全3回で構成されている「スポーツビジネス入門」の第2回です)
ビジネスモデルの基礎
「ビジネスモデル」という言葉は、ニュースやビジネス書籍などで頻繁に登場しますが、「具体的にどういう意味?」と聞かれると、答えに詰まってしまう人も多いかもしれません。特にスポーツの世界では、「プレー」や「運営」の話が中心になりやすく、ビジネスモデルを構造的に考える機会が少ないのが現実です。
しかし、スポーツを仕事にする上では、「どのように価値を生み、お金を得て、持続させていくか」を理解することが重要です。
ビジネスモデルとは
ビジネスモデルとは、一言でいうと「価値を生み出し、それを収益に変え、継続的に提供する仕組み」を指します。少し分解すると、以下のような要素が含まれています。
- 誰に(ターゲット)
- どんな価値を(提供価値)
- どうやって届けるか(チャネル・仕組み)
- どうやって利益を得るか(収益モデル)
このように、誰に・何を・どうやって・どう稼ぐか、をセットで考えることが「ビジネスモデルの設計」です。
スポーツ業界における主なビジネスモデル
(1)プロスポーツチーム
- 価値提供:感動・エンターテイメント・地域貢献
- 主な収益:チケット販売、スポンサー収入、放映権、グッズ売上など
- 特徴:ファンとの関係性が重要、マスメディアとの連携が多い
(2)スポーツスクール・クラブ
- 価値提供:運動機会、教育、技術指導
- 主な収益:月謝・入会金、イベント参加費、教材や用具の販売
- 特徴:保護者との信頼関係が重要、地域密着型が多い
(3)スポーツイベント事業
- 価値提供:参加体験、交流の場、非日常の演出
- 主な収益:参加費、協賛金、物販、委託費など
- 特徴:収支構造がプロジェクト単位、コスト管理が重要
(4)メディア・配信型ビジネス
- 価値提供:情報・映像コンテンツ
- 主な収益:広告、視聴料、ライツ(映像使用料)
- 特徴:デジタル活用、他業界との連携が進む
成功するビジネスモデルに必要な視点
成功するビジネスモデルには、以下のような要素が必要です。
- 顧客視点(本当に求められているか?)
- 収益性(きちんと利益が出る構造か?)
- 継続性(長く続けられるか?)
- 独自性(他と差別化できるか?)
また、社会的価値や地域とのつながりなど、「数字には見えにくい価値」も大切にしながら全体を設計することが、スポーツビジネスでは特に求められます。
マーケティングの基本
「マーケティング」と聞くと、広告やSNSなどの「宣伝活動」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし本来のマーケティングとは、「顧客が本当に欲しいものを提供するための一連の仕組み」を意味します。
ピーター・ドラッカー(経営学者)の有名な言葉に「マーケティングの理想は販売を不要にすることである」というものがあります。
これはつまり、「顧客のニーズに合った商品やサービスをつくれば、無理に売り込まなくても自然に選ばれる」という考え方です。
スポーツビジネスにおいても、マーケティングはファンを増やし、事業を成長させるうえで欠かせない考え方です。
マーケティングとは
マーケティングという言葉は、「営業」や「宣伝」と混同されがちですが、それらはマーケティングの一部に過ぎません。
マーケティングは、もっと広い意味で、「価値をつくって届ける活動全体」を指します。
例えば、スポーツイベントを例に挙げると、
- 誰をターゲットにする?
- どんな体験を提供する?
- どこで・どう伝える?
- 価格は?来場動機は?
- ファンにリピートしてもらうには?
このような「戦略」と「設計」がマーケティングの仕事です。
マーケティングの4P
マーケティングを理解するうえで基本となるのが「4P」というフレームです。
これはビジネスにおける4つの重要な要素を指します。
① Product(製品・サービス)
何を提供するのか?
例:試合観戦、イベント、グッズ、スクール、コンテンツ
② Price(価格)
いくらで提供するのか?
例:チケット代、会員費、サブスク、無料と有料の使い分け
③ Place(流通・チャネル)
どこで・どのように届けるのか?
例:スタジアム、オンライン、アプリ、店舗、SNS
④ Promotion(販促活動)
どうやって認知してもらうか?
例:ポスター、CM、SNS投稿、ファンイベント、インフルエンサー連携
この4Pは「売る側の視点」ですが、近年は顧客視点の「4C(Customer, Cost, Convenience, Communication)」という考え方も重要になっています。
スポーツビジネスにおけるマーケティングの特徴
スポーツならではのマーケティングには、一般的なビジネスとは異なるポイントがあります。
【1】感情が動く「体験価値」が中心
スポーツは“商品”というより“体験”
喜び・悔しさ・感動など、感情がマーケティングの鍵
【2】ファンとの「関係性」が資産
一度の購入よりも、継続的な応援(リピート・共感)が重要
顧客は「観客」から「ファン」へ、さらに「サポーター」や「仲間」に進化する
【3】時間・季節・場所に左右されやすい
試合日や天気、対戦カードによって動員が変動
オフシーズンの工夫や地域イベントとの連携が必要
全ての出発点は「ターゲットの理解」
マーケティングで最も重要なのは「誰に届けるか」というターゲティングです。
例えば、以下のように顧客層を細かく分けて考えると、アプローチが変わります。
- 小学生とその保護者 → ファミリー向け割引や体験イベント
- 熱心なサポーター → 限定グッズや選手交流会
- ビジネス層 → VIP観戦席や接待向けパッケージ
また、ペルソナ(理想的な顧客像)を設定することで、施策に一貫性を持たせやすくなります。
SNS・デジタルマーケティングの重要性
現代のスポーツマーケティングでは、SNSの活用が不可欠です。
SNSのメリットとしては主に以下が挙げられます。
- 情報を即時に拡散できる
- ファンと直接コミュニケーションできる
- コンテンツを通じて共感や熱量を醸成できる
Instagram、X(旧Twitter)、YouTube、TikTokなど、プラットフォームごとに使い分けることが効果的です。
また、近年ではLINE公式アカウントや独自アプリ、ファンコミュニティなども活用されています。
スポーツマーケティングの事例
①川崎フロンターレ(Jリーグ)の地域密着戦略
地域イベントや学校訪問を積極的に実施
サポーターが「地元の誇り」として応援
②NBAのグローバル展開
SNSやYouTubeを活用して国際ファンを獲得
選手のストーリー性や個性も発信
③ラグビーワールドカップ日本大会(2019)
「にわかファン」を歓迎するSNS戦略
「一緒に楽しもう」という姿勢で共感を生む
これらは、「誰に・何を・どう伝えるか」を的確に設計していた点が成功の要因です。
収益の仕組み
スポーツの世界は「情熱」「感動」「夢」が詰まった舞台ですが、それだけでは持続できません。
チームやイベント、施設の運営には人やモノ、時間が関わり、当然「お金」が必要です。
では、スポーツの現場では どのようにしてお金を稼ぎ、回しているのでしょうか。
スポーツも「ビジネス」である
まず大前提として、スポーツの世界も一つの「ビジネス」です。
選手の活躍や観客の感動を支えているのは、裏でしっかりとした収益構造があるからこそであり、チーム運営もイベントも「事業」として継続可能でなければ、ファンに価値を届け続けることはできません。
したがって、「収益をどう得るか?」はスポーツに関わるすべての人にとって重要な視点です。
プロスポーツチームの主な収益源とは?
プロスポーツチームの収入にはいくつかの柱がありますが、代表的なものは以下となります。
(1)チケット販売(観客動員)
試合観戦チケットやシーズンパスなど、ファンが「試合を観たい」という思いに対して、お金を支払います。
- 単価×動員数=収益
- ファンが増えるほど売上も増える
- 天候・成績などに影響されやすい
(2)スポンサー契約(広告価値)
企業が「チームや選手を応援し、自社のPRを行う」ために契約します。
- ユニフォームロゴ、看板、公式SNSなどで露出
- ブランドイメージやCSRにも活用
- 信頼や影響力が高いほど高額に
(3)放映権料(テレビ・配信)
試合をテレビやネット配信で放映するための契約料です。
- 視聴者数や人気の高さが影響
- Jリーグ・プロ野球・五輪などで大きな収入源に
- 最近はYouTubeやSNS配信も活用
(4)グッズ販売(物販・EC)
チームグッズやユニフォーム、限定商品など、会場・オンラインショップ両方で展開しています。
- 熱量の高いファンほど購入率が高い
- 流行やコラボ企画などで売上UPも
(5)その他(地域事業、スクール等)
スポーツ教室、地域連携イベント、講演、BtoB案件など、地域との関係性を深める活動がメインです。
- 育成・教育事業としても展開可能
- 社会的意義と収益を両立する取り組み
アマチュアスポーツやイベントの収益
プロと異なり、アマチュアチームや地域のスポーツイベントでは、次のような収益構造があります。
(1)参加費
大会・イベントの参加費が主要な収益源。人数と設定価格で売上が決まります。
(2)助成金・行政の補助
市区町村やスポーツ振興団体からの支援を受ける場合も。
(3)協賛金(スポンサー)
地元企業や商店街とのタイアップで資金を得るケースもあります。
(4)物販・飲食ブース
大会Tシャツやドリンク販売など、会場内での物販も収入源の一つです。
収益とミッションのバランス
スポーツビジネスでは、「利益の追求」と「社会的意義の実現」のバランスも重要です。
例えば、スクール事業や地域活動は、直接的な収益は少なくても、
- チームの認知拡大
- ファンづくり
- スポンサーとの信頼構築
など、間接的な価値を生み出します。
「お金を稼ぐため」ではなく、「良いサービスを届けた結果としての収益」という意識を持つことが、長期的な成功に繋がります。
コストと利益の考え方
ビジネスを行う上で欠かせない「利益」です。
利益を生み出すには、単に売上を増やすだけでは不十分なため、コストを理解し、適切に管理することで、はじめて健全な収益構造が実現します。
スポーツビジネスでも、イベント運営やチーム運営、スクール事業など、さまざまな場面で「収支管理」が求められます。
利益とは
利益とは、売上(収益)から費用(コスト)を引いたものです。
この「利益」は、大きく以下の3種類に分かれます。
①売上総利益(粗利益):売上 ー 原価
たとえばグッズ販売なら、売値から仕入れ値を引いた金額
②営業利益:売上総利益 ー 販管費(人件費や広告費など)
通常の事業活動で得られる利益
③経常利益/純利益:営業利益から、金利や税金なども引いた最終的な利益
スポーツチームでも、チケット収入やスポンサー収入から、選手の年俸、運営費などを差し引いて最終的な利益を算出します。
主なコストの種類
スポーツビジネスにはさまざまなコストが発生します。
それらは大きく分けて、以下のようなものがあります。
【1】人件費
選手やコーチ、運営スタッフの給料や報酬。
特にプロスポーツでは選手への報酬が大きな割合を占めます。
【2】運営費
試合やイベント開催にかかる費用。
会場の使用料、機材レンタル、交通費など。
【3】広告・宣伝費
集客のための広告出稿費、SNS運用、デザイン費など。
【4】制作費・備品費
ユニフォームやノベルティグッズの制作、会場設営に使う道具の購入など。
【5】その他の費用
保険、登録費、通信費、システム利用料など。
「固定費」と「変動費」の違いと「損益分岐点」との関係
コストはさらに、固定費と変動費に分けられます。
- 固定費:売上の大小に関係なくかかる費用(例:施設使用料、常勤スタッフの給料)
- 変動費:売上や活動量に応じて増減する費用(例:イベントで使う備品や材料費、参加者1人あたりのノベルティ代)
この違いを知ることで、「損益分岐点(=黒字になるライン)」が明確になります。
「損益分岐点」とは、売上と費用がちょうど同じになる点のことで、このラインを超えると黒字、それ以下だと赤字になります。
簡単な損益分岐点の求め方としては、「損益分岐点売上 = 固定費 ÷(1 − 変動費率)」です。
例えば、小規模なスポーツイベントにおいて、
- 固定費:30万円(会場代・スタッフ人件費)
- 1人あたりの変動費:1,000円
- 参加費:1人 3,000円
とした場合、1人当たりの利益が2,000円となるので、150人(30万円 ÷ 2,000円) 集客できれば黒字になるという計算ができます。
利益を出すには
利益を出すための基本は、シンプルに以下の2通りです。
①売上を増やす
例:集客数を伸ばす、単価を上げる、リピーターを増やす
②コストを抑える
例:無駄な経費を削減、ボランティア活用、補助金の活用
ただし、やみくもな削減はNGで、クオリティを落とせば顧客満足度が下がり、逆効果になることもあります。
重要なのは、コストを「投資」と捉えて、成果が見込める部分に集中することです。
組織と人材の基本
スポーツの現場といえば、真っ先に思い浮かぶのは選手や監督かもしれません。
しかし、実際のスポーツビジネスは、選手だけでなく、数多くの「裏方」の支えによって成り立っています。
主なスポーツ組織の種類
スポーツに関わる組織は実に様々です。
それぞれの目的や規模によって、組織の作り方や運営スタイルが異なります。
プロチーム(例:Jリーグ、プロ野球、Bリーグなど)
営利企業として、興行やビジネスを目的とする
総合型地域クラブ(例:市民クラブ、スポーツ少年団など)
地域住民の健康・交流が主な目的
NPO法人(例:スポーツ振興団体、教育団体など)
公益性重視、非営利で活動する
企業チーム(例:実業団チーム)
自社PRや社員育成が目的
組織の主な部門と役割
スポーツ組織を「会社」として見立てると、以下のような部門に分かれます。
【運営部門】
GM(ゼネラルマネージャー):組織全体のマネジメント
事務局:スケジュールや書類などの運営全般
会計・人事:お金や人材の管理
【実行部門】
イベント企画・運営:試合やイベントの準備・実施
広報・SNS担当:情報発信やメディア対応
営業・スポンサー対応:資金調達、企業連携
【技術部門】
指導者(コーチ):選手への技術指導
トレーナー:フィジカルやメンタル面のサポート
【外部連携】
地域・行政との窓口:地域貢献や助成金対応
ボランティア管理:協力者との調整・指導
スポーツ業界で求められる能力とは
スポーツビジネスで活躍するには、「好き」や「情熱」だけでは不十分です。
実務や対人スキルなど、ビジネス的な能力も重要になります。
- コミュニケーション力:チーム内外との連携、協力者との信頼構築
- 柔軟性・対応力:現場でのトラブル対応や変化への即応力
- ビジネススキル:収支管理、提案資料作成、契約・交渉など
- マネジメント能力:人や予算、タスクの管理
- SNS・ITリテラシー:情報発信や集客、データ活用のためのIT知識
- スポーツへの情熱・理解:スポーツ特有の文化や価値観の理解
現場を支える多様な人材
スポーツ業界には、フルタイム職員だけでなく、様々な形で関わる人たちがいます。
- アルバイト・パート:受付・運営スタッフ
- ボランティア:イベント協力、広報補助など
- インターン・学生スタッフ:現場体験の場
- 外注業者:警備、デザイン、映像など専門職
「人材が多い=コストも高い」ですが、それをどうチームとして束ね、活かせるかが運営のポイントになります。
組織の課題と工夫
スポーツ組織には、次のような課題もあります。
- 人手不足(特に事務局系)
- 専門性の高い人材の確保が難しい
- 若手人材の育成と定着
- 組織の成長=収益の安定と連動していない
これに対し、
- 外部連携(大学・企業・行政)による協力体制
- IT活用(タスク管理・会計システム)
- 若者向け研修やキャリア支援
などの工夫で、少人数でも効率的に運営する事例も増えています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、より詳細に実例も交えながら、スポーツビジネスをより深く学んでもらう回となりました。
本コラムを読んで感じた方も多いと思いますが、「スポーツ業界だから」ということではなく、他業界と同じように求められるスキルや知識は同じです。
そのため、スポーツ業界で活躍できる人は他業界でも活躍できますし、その逆も同様です。
次回は、この2回で学んだことの応用編として、スポーツ業界特有のビジネスモデルをご紹介していきます。


